競馬の儲けと税金―申告・課税のしくみと裁判・捜査事例まとめ

かつて競馬は「夢を買う娯楽」という側面が強く、的中しても小遣い程度の利益というケースが大半でした。しかしここ数年、年間で数百万~数千万円単位の利益を出す個人が少しずつ増えてきています。その背景には、三連単という高額馬券ができたのもありますが、それよりもかつての「勘と経験」頼みの予想から、データとテクノロジーを駆使した分析型予想への移行が大きな要因として挙げられるでしょう。
特に JRA-VANの公式データ提供 や TARGET frontier JV のような競馬データベースソフトの普及、さらにAI解析による展開予測や買い目提案ツールの台頭により、精度の高い予想が可能になりました。また、ネット投票や即PATなどのシステムが整備されたことで、地方に住むファンでも簡単に全場・全レースにアクセスできるようになり、購入機会や資金運用の自由度も格段に向上しています。
実際、数千万円~億規模の払戻金を巡って税務当局による調査や裁判がこれまでにも報じられており、これが「もはや他人事ではない現実」であることを示しています。こうした事情を踏まえつつ、以下では競馬に関連する税務上の仕組みと主な裁判・実例、そして現実的な対応策をまとめます。
 申告・課税の仕組み|一時所得と雑所得の違い
申告・課税の仕組み|一時所得と雑所得の違い
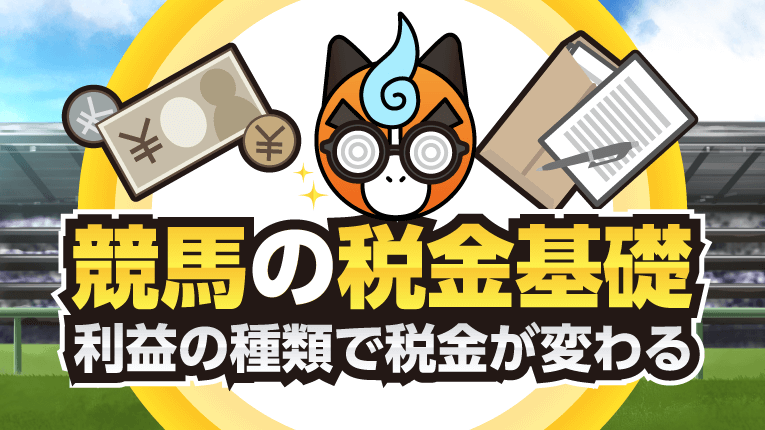
競馬で得た利益は「非課税」ではありません。一定の条件を満たす場合には、所得税や住民税の課税対象となります。主に関係するのは「一時所得」と「雑所得」の2つですので、まずは両者の概要や違いについて理解しておきましょう。
一時所得として扱われる場合
これは臨時的に得た利益が該当し、競馬では単発の的中や、継続性のない購入方法による配当が当てはまります。計算方法は以下の通りです。
一時所得 =(的中による払戻金 - その馬券の購入費 - 特別控除額50万円)× 1/2
例えば、1年間の払戻金合計が200万円、馬券購入費が120万円の場合、
(200万円 - 120万円 - 50万円)× 1/2 = 15万円が課税対象額になります。
この課税額に所得税・住民税がかかります。
ただしこの方式は、年間を通じた回数や継続性が少ない場合に適用されるのが原則です。
雑所得として扱われる場合
これは、競馬を継続的・組織的に行い、利益を得ることを目的としていると見なされた場合に適用されます。AIやデータベースを使い、大量の馬券を年間通して購入するケースなどが典型です。
雑所得の場合、経費計上の範囲が広がり、交通費やデータサービス利用料なども必要経費として認められる可能性がでてきます。その一方で、一時所得のような50万円の特別控除は使えません。課税額は以下の式で求められます。
雑所得=(払戻金の合計 - 必要経費)
そして雑所得は総合課税となり、他の所得と合算されて税率が決まります。利益規模が大きければ税率が上がる可能性も高まるため、高額利益を出す人ほど税務リスクが大きいといえます。
また、ここで言う「必要経費」にはずれ馬券が含まれるかどうか、という点での認識の違いが、過去に裁判で争われています。
 申告の必要性とその方法
申告の必要性とその方法
競馬で年間を通じて利益が出た場合、原則として確定申告が必要となります。ここを軽視してしまうと、後に税務署からの指摘や追徴課税、場合によっては重加算税といったペナルティを受ける可能性があります。確定申告が必要となる基準を、簡単にまとめておきます。
一時所得の場合
一時所得は50万円の特別控除がありますが、この控除後の課税対象額が0円以下でない限りは申告が必要です。例えば、G1レースで高額的中を一度だけ出した場合でも、その利益が大きければ確定申告の対象となります。
雑所得の場合
特別控除はないため、年間の利益が少額であっても、利益が出ていれば申告義務があります。
継続的な馬券購入を行う人、予想ソフトやAIを活用している人は雑所得扱いになるケースが多く、ほぼ確実に申告が必要です。
確定申告においては利益計算のためのエビデンスが欠かせません。JRAのネット投票(即PATなど)を利用していれば、投票履歴や精算履歴をダウンロード可能です。これらを利用して年間の払戻金と購入額を集計しましょう。
また、雑所得として経費計上する場合は、交通費や予想紙の購入費、データツール利用料などの領収書も併せて保管しておきましょう。税務署からの質問に備えて「なぜその費用が競馬に必要だったのか」を説明できる状態が理想です。
紙馬券の場合は、的中馬券や購入レシート、または競馬場・WINSでの払戻明細を保存しておく必要がありますが、これを律儀に行っている人はほとんどいないのが現実です。
申告しないとどうなる?
申告を怠ると、過去に遡って税務調査が行われる可能性があります。追徴課税の他、悪質と判断されれば重加算税(最大40%)や延滞税が課されることも可能性としては考えられます。
実際に、ネット投票記録から高額的中が判明し、数年分まとめて税務署から指摘を受けたケースも報道されています。これらの事例は「知らなかった」では済まされません。
 過去の裁判事例
過去の裁判事例

競馬の払戻金と税金を巡るトラブルは、もはや珍しい話ではありません。特にインターネット投票の普及以降、高額的中や継続的利益を得る人が増え、税務署や裁判所が脱税と判断を下すケースが増加しています。ここでは代表的な事例を紹介し、そこから見える注意点を解説します。
https://www.bengo4.com/c_15/n_398/
数ある判例の中でも有名なのが、大阪地裁で争われた競馬予想ソフト利用者の課税事件です。
この男性は予想ソフトを活用し、年間を通じてかなりの頻度で馬券を購入していました。結果的に28億円強の払戻金を得て、1億4000万円ほどの利益を得ていたのですが、税務署はその全てを一時所得と認定し、経費として馬券購入費を認めませんでした。(厳密には、「当たり馬券」の購入費は経費として認めつつも、はずれ馬券は認めないというもの)
結果的には、継続的かつ営利目的で馬券購入を行っていたため「雑所得」に該当し、必要経費としてはずれ馬券購入額も差し引けると判断され、脱税額は約6億円から5,000万円にまで大幅に減額されました。この判例は、その後の競馬課税の考え方に大きな影響を与えています。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025061100523
東京国税局は2025年6月、競馬などの公営ギャンブルで約6億1,200万円を得ながら、約2億6,200万円を申告せず脱税した疑いで、サッカーJ3クラブ元会長である57歳の男性ともう1名を、所得税法違反容疑で東京地検に告発しました。
2人は、知人が開発・提供した独自の馬券自動購入システムを駆使し、月20億円に及ぶ投票を機械的に実行。約60名義を使って分散投票することで、実際の利益を隠蔽していたとされます。
この事件では、名義を分散させた購入構造に加え、利益の大部分が香港在住の指示役に渡っていた点が特徴です。報道によれば利益の9割は海外に流れ、購入役の2人には1割のみが分配されていました。
このスキームにより、税務署による課税追及や処理が難しくなる構造が出来上がっていたと言えます。
いずれの事例も、税務署を甘くみていた結果が招いたものです。こういった事例が増えている今、これまで以上に税務署も競馬でのお金の動きにも敏感になっているはずです。
税務署は、銀行口座の入出金や公営競技のネット投票履歴、さらにはSNSの発言などからも情報を収集します。特にJRAや地方競馬のネット投票システムは全てログが残るため、後からまとめて調査されることも珍しくありません。
「バレないだろう」という考えは極めて危険であり、むしろ記録が明確な分、発覚リスクは高いと言えるでしょう。
 まとめ
まとめ
近年、AIや自動購入プログラム、データ解析を活用することで、競馬で安定した利益を上げる人が確実に増えています。実際に数千万円から億単位の利益を出した事例もあり、夢物語ではない世界が広がっています。
しかし、利益を出すことと、それを手元に残すことは別問題です。今回紹介した事例のように、税務申告を怠れば脱税となり、追徴課税や刑事罰の対象になる可能性があります。競馬で得た収益は、基本的に一時所得または雑所得として課税対象となるため、どの区分に該当するのかを正しく判断し、必要な経費計上や確定申告を行うことが欠かせません。
競馬予想サイトやツールを駆使して勝ちを積み重ねるのももちろん大事ですが、その利益を守るために税金や法律の知識も身につけておきましょう。
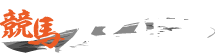





 Alohaな競馬
Alohaな競馬 五十嵐アキラの快刀乱麻
五十嵐アキラの快刀乱麻 大五郎のたわ言
大五郎のたわ言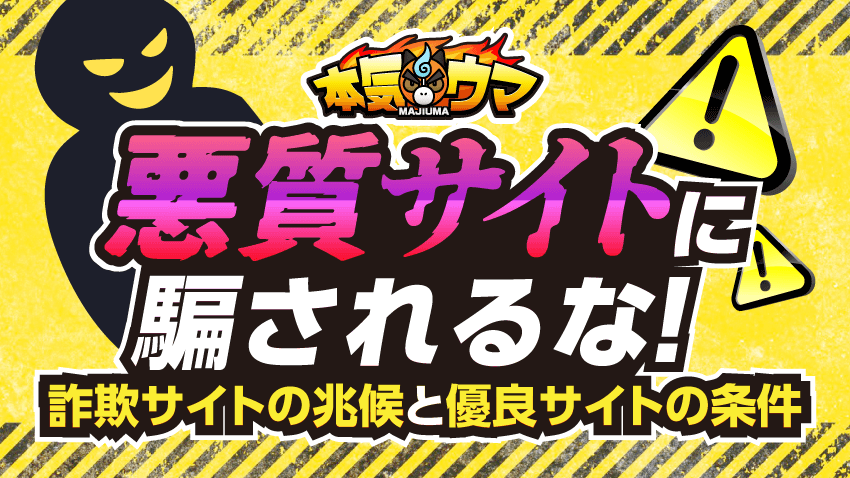
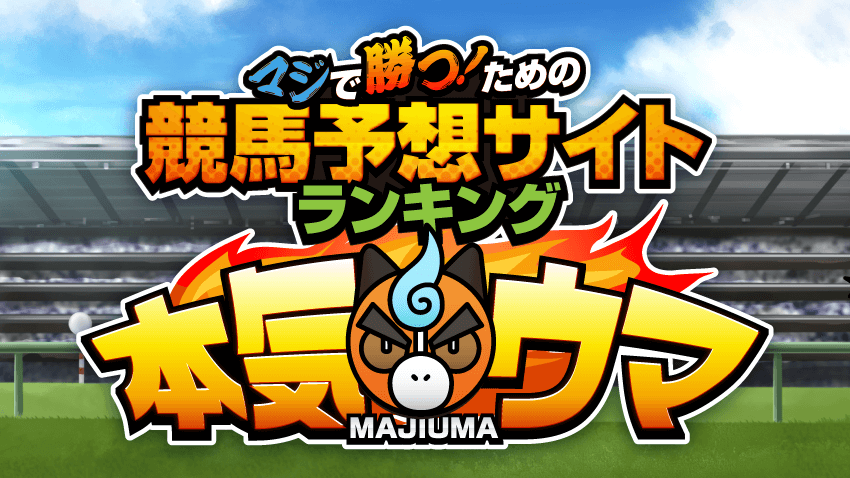



 初心者の方へ
初心者の方へ お楽しみコンテンツ
お楽しみコンテンツ